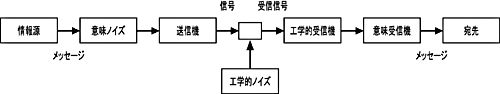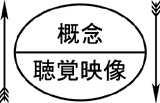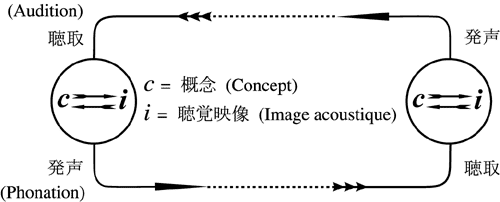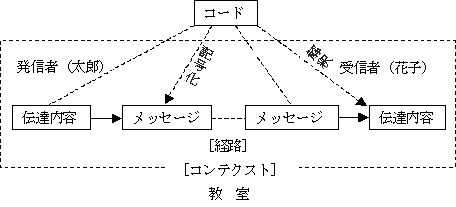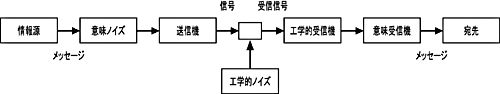
図2 コミュニケーション・モデルA(Shannon & Weaver 1949: 37より作図)
| 記号論 | ロック、パース、モリスの 系譜 | |
| 記号学 | ソシュールにはじまりバルトに至る系譜 |
| 前者は諸記号間の関係、記号と指示対 象の関係の分析等、制度としての記号内現象を主たる対象とする。後者では言語のみならず、人間の表情・身振り、芸術作品、神話・伝説、宗教とその 付属物、メディアとその表示物、建造物、都市、つまりは人間の被造物である文化一般、そしてときには自然をも記号として捉え、これらの人間にとっての 本質的な意味と、これらにかかわる人間行動とを研究の対象としている。マス・メディア接触を含むコミュニュケーション行動のみならず、何らかのもの・こ と・ひとに対する社会行動にはつねに広義の意味が介在している。むしろ意味なしの行為などありえない。従って記号論・記号学の知見は社会的存在とし ての人間の行為の理解に寄付している。 | |||
| -----濱嶋、竹内、石川編『社会学小辞典』(有斐閣 1997) | |||
| 「すべては対立として用いられた差異にすぎず、対立が価値を生み出す」 |
| もし、ナイト(騎士で将棋の桂馬に相当)の駒をなくしてしまっても、手近にある別の道具で代用できる。ナイトのように 馬の上半身の形をしていなくてもいい。別の余っている駒に目印を付けてもいい。区別がつけばいいのだ。つまり、対立があれば十分なのである。チェスのキン グの価値というのは全方向へ動くことができて、取られたらゲームが終わりである。しかし、どこにいるか?何が残っているか?相手はどこにいるか?など局面で 大きく価値が異なる。 |
| ゲームのそれぞれの状態は言語の一つの状態に対応している。それぞれの駒の価値はボードにある位置によって決定される。言語においても、それぞ れの語の価値は、他の全ての語との対立によって決まる。 |
| /|記号|→|意味1|/→|意味2| |