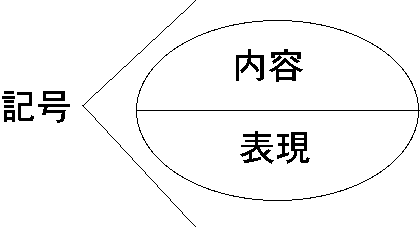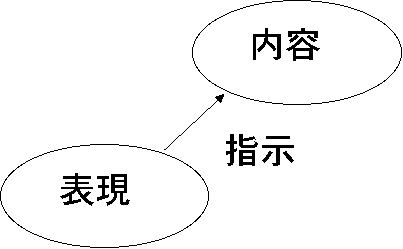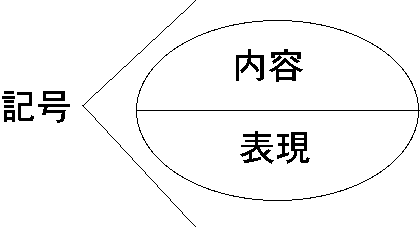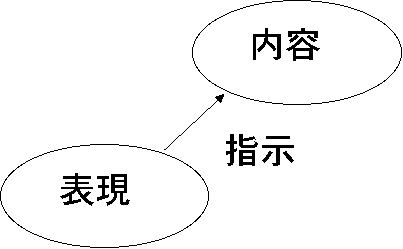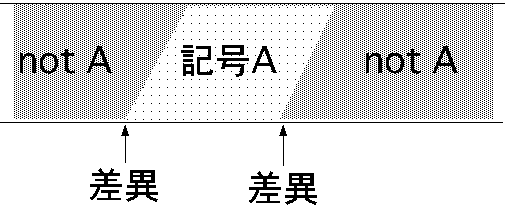(7)記号と情報理解のモデル
記号学は情報と情報を処理することを理解するのに有用な手立てである。情報を記号学の視点からとらえる方法と、その意義、効果をとりあげる。
1 情報とは
- Data
- Information
- Knowledge
- Intelligence
Information, Knowledge, IntelligenceをいかにDataへと置き換えることができるか
人にとって情報とは、「意味」としてもたらされるのであり、情報の問題を考える上で、「意味」の発生に関わるプロセスや、そのプロセスを成立させる条件も重要である。「意味」を読み取る人間がいなければ、情報は存在しない。
| | 意味発生の原理的側面に関する学問 |
| | → | 哲学、言語学、記号学(論)etc. |
| | 意味の社会的次元に注目する学問 |
| | → | 社会学、人類学 etc. |
| | 人にとっての情報と技術との関連に注目する学問 |
| | → | メディア論 |
| | 人にとっての情報を科学的視点から捉える学問 |
| | → | 認知科学 |
| | より具体的な教育活動に結びつくもの |
| | → | メディア・リテラシー |
- Information、Knowledge、Intelligenceといったものは、「物事の意味」と深い関連がある
- 「意味」は「表現」と密接に関連する
- 記号学は「意味と表現」とを考える学問
人間の認識のありよう(認識論)と、認識によって捉えられる物事のありよう(存在論)に結びつく
実証科学(経験科学)としての認知科学と密接に関連する
記号学は“人にとっての情報”を議論するための一つの土台を提供する
2.1 基本概念
記号論で扱われる「記号」とは何か?
身の回りの記号をいくつか挙げてみよう。
- 交通標識
- ト音記号
- 禁煙の表示
- 言語
極めて洗練された記号体系
- 時計
絵画のなかに意味ありげに描かれた時計は、規則性や几帳面さを表す記号
ダリが描くデフォルメされた時計は時間という秩序の崩壊を意味する記号
- 椅子
玉座としての椅子は権力の象徴としての記号
- ハト
ノアの洪水の終結を知らせた平和の象徴
- ペン
言論による力を表す記号
- 衣服
ノーネクタイは格式・形式を排除した気楽さの記号
※ 記号とはそれが何か他のものを意味する限りにおいて記号となる
したがって、記号が成り立つには、記号とされるモノと、それで表される他の何かが必要である。
記号は、“意味(内容)”と“表現”の二つの側面を持つ。“意味(内容)”と“表現”は常に不即不離の関係にある。
モノそのものが記号なのではなく、モノとそれによって指示され、意味される対象との関係が記号を成立させるのであるから、その両者の関係が記号論においては重要なのであり、記号論が扱うのはモノそれ自体ではない。
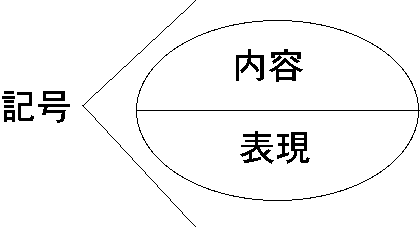
以下の発想との違いが重要
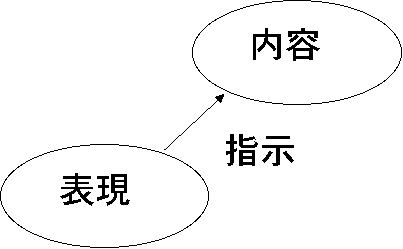
※ 記号論が問題にするのは記号を通して透けて見える関係性である。
単一的な具象物、抽象的な概念、言語、複合的な表出(たとえば複数の単語からなる文章や、視覚や聴覚を刺激する映画など)、われわれの経験(時間的空間的体験)さえも記号といえる。こうした記号化の作用、それは人間の構想力(と解釈力)に関わる根源的な問題であり、それらを問い直すのが記号論である。記号論を導入することによって、これまで見えていなかった世界が見えるようになり、世界観そのものが変わる.
- 認識されるのは常に記号そのもの
“意味(内容)”と“表現”との区別は、事後的な分析によってはじめて見いだされる
- “内容”と“表現”との結びつきに必然性はない
それらの結びつきは、文化的な約束事(コード)によってのみ保証される(恣意性の原理1)
| 例 | <犬(内容)>を「イヌ(表現)」と呼ばなければならない必然性(自然的根拠)はない |
- 記号は常に他律的な存在
記号の認識は、他の記号との“差異”を通してのみおこなわれる
| 例 | 「学生」という記号の意味は、他のあらゆる「学生でないもの」との差異によってのみ認識される |
(記号Aの存在は、あらゆるnot Aの存在によってのみ保証さ れる。下記を参照)
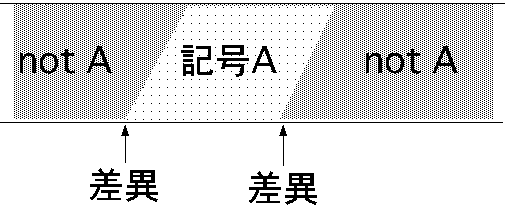
- 世界から記号を見いだす働きを“分節(articulation)”と呼ぶ
記号が見いだされる以前の世界は、モノやコトの区別の存在しない“連続体”(カオス)
“連続体”に分節線を引くことにより、記号が見いだされる
分節とは、カオスに何らかの秩序を与える行為
秩序は、文化的な構築物であるコードによって(のみ)与えられる(恣意性の原理2)
- コードとコンテクストの相補的関係
コードの拘束力は絶対的でない
コンテクストの介入によって、コードの与える分節線は変化する
例えば「ありがとう」の意味は、発話のコンテクストによって異なる
2.2 記号学から見た“読むこと”と“表すこと”
- 表現も意味も、読み取られてはじめて実在が許される
分節のないところには表現も意味もない
- 表現や意味の認定権(あるいは決定権)は、原理的に“読み手”の側にある
「何が「表現」として認識されるか」「どのような意味が読み取られるか」は、読み手によって読み取られた通りでしかない
“表し手”の手を一旦離れたものは、原理的に制御不能
- “表すこと”は“伝えること”を保証されていない
表現と伝達とは本質的には別々の行為
例えば、“本の内容”はあらかじめ存在しない(形而上的存在としての「客観的意味」の否定)
「表現と意味(内容)の不可分性」は、「形而上(the physical)・形而下(the metaphysical)の絶対的な分化」を否定する
従来の形而上学的認識・・・表現(形而下の存在)には、その本質的としての意味(内容・形而上の存在)が付随する
表現すなわち意味は、読み手との関わりと無関係には存在しえない
2.3 記号学の提示する世界観
- 世界は記号(=意味)によって構成される
人は分節を通してのみ世界を認識しうる
私たちが認識しているのは、分節されたあとの世界
- 分節の秩序(=コード)が、(認識される)世界のあり方を決める
コードの有り様によって、世界はいかようにでも姿を変える
文化・習慣・世界認識の違いは、コード間の差異に還元される(例えば「先進文化と未開文化」といった対立の捉え直しに結びつく)
- コードを形成するのは、個々の具体的な分節の実践
私たちの側が積極的に働きかけることにより、コードに変化がもたらされる可能性もある
ゆえに、私たちの意識的な実践によって、世界の姿が変化する可能性もある(例えば意図的、あるいは偶然的なコードの逸脱)
分節の、世界に対する積極的な働きかけとしての側面を、特に「意味づけ」と呼ぶ
- 人間の存在と無関係に意味(=情報)は存在しない
意味は分節とともに生まれる
例えば私たちとは無関係に「イヌ」は存在しない
絶対的な意味での「客観的情報」は存在しない
2.4 記号学の考察対象
- 言語
- 神話・物語(思考・行動を支配するメタ・コードとしての)
- 文化的慣習(例えば宗教意識とタブーについて、身振り・所作の儀礼的意味、食文化、交換(経済)のあり方・社会制度のあり方など)
- 芸術
- その他の人工物(例えば建築物、民具などの物質文化、ファッション、メディアテクスト、ソフトウェア、その他有形無形のあらゆる人工物)
“言葉的なもの”として捉えられるあらゆる現象 は考察対象となりうる
2.5 記号学的発想から見た日常世界の情報
例1「授業の選択」と情報
- あとから振り返って、「授業の選択」に影響を与えた“情報”とはいったい何だったか
- その“情報”を手に入れたとき、本当に“情報の収集”を意識していたのだろうか
- 「情報収集」という観点から振り返った時に、見落とされたものはないだろうか(例えば授業のタイトルの記号性は?)
- “慣習(あるいは「これまでのやり方」に基づく先入観、視野を限定する漠然とした要因)”はどれだけの影響力を持ちうるか
例2「テレビの視聴」と情報収集
- テレビを見ているときに、「情報の収集」をどれだけ意識しているだろうか
- 結果的に“情報”として役だったものは、どのような経緯で頭の中に入ってきたか
例3「メモを取る行為」と情報の生成
- 「メモを取る行為」は一見すると情報の生成に結びつく
- しかしながら、「メモとして取られたこと」は、無条件に“情報”たりうるか
- 「メモを取る行為」自体の動機に、“情報”という要因はどれだけ関わっているか
例4「ホームページを出すこと」と情報の発信
- 「ホームページを出すこと」は、情報の発信とどの程度関連するか
- 「ホームページ」、「ホームページを持っている人」、「ホームページを持っていること」は、どのような記号性を有するか
- 「ホームページを出すこと」が情報の発信に結びつくためには、どのような条件が必要か
3 情報教育に記号学を取り込む意義
- “情報”が無条件には存在し得ないものであること
- “情報の収集・整理・発信”は、きわめてintentionalな行為でなければならないこと
例えば“読む”という行為自体は、非常に慣習的(かつ無意識的)な側面を持っている
また、その際の私たちの視野は自ずとコードによって限定されている
そのような“読む”という行為と、“情報の収集”との間に、本質的な境界線は引けない
従って、その境界線は、私たちが意図的に引いてゆかねばならない
- 情報発信を試みる際に考えるべきこととして、以下のことを学ぶことができる
情報は、読み手なしには存在し得ないものであること
読み手がいたとしても、それが情報として生かされるかどうかには、何の保証もないこと
- これらを通して、逆に、“情報とは何か”についてを問い返す契機となる
“情報”を出発点(前提)としない情報教育
学習者自らが“情報とは何か”についてを考える(考えざるを得ない)
4 メディアテクスト分析の方法としての記号論
- 「記号論の視点」のキーワード
- 記号、メッセージ
- メッセージとコード
- コード化された表現
- メタメッセージ(コノテーション)
- コードとコンテクスト
- 「受け手」の位置づけ
- 記号論的分析の一般的な目的
分析対象の「記号としての効用」を明らかにする
メッセージ解読の「暗黙の前提(支配的なコード、コードを支える価値観、etc.)」を明らかにする
- 記号論的分析の一般的な手続き
「現実の読み手による解読」を解読する
- 対象の発する(であろう)メッセージの記述
- メッセージを形成する記号(=コード化された表現)の発見
- コード化を可能にするコード、コードを支える価値観の推測・記述
4.1 記号論的分析
分析例
- “この写真”からは、どのような印象を受けるか
- テキストとの組み合わせにより、写真の発するメッセージはどう変わるか
- 広告全体のメッセージとコード化された表現との組み合わせとしては、いかなるものが見いだされるか
- コード化された表現は、いかなる表現技法によって支えられるか(メッセージに“関与的”な表現技法)
- オルターナティブな表現として、どのようなものが考えられるか。また、そのような表現を導入することで、メッセージはどのように変質するか
- この広告は、全体としていかなるメタメッセージを伝えるか。また、そのメタメッセージはいかなる価値観によって支えられているか
- そのような価値観が前提とされることで、広告の表現全体からは何が排除されているか
解答例